ムラサキミミカキグサ(紫耳掻き草)
【かぎけんWEB】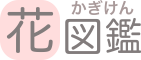
花図鑑をリニューアルしました。
上記リンクにてアクセスできます。
|
ムラサキミミカキグサ(紫耳掻き草)は、北海道〜九州の湿原に生えるゴマノハグサ目タヌキモ科タヌキモ属ミミカキグサ種の匍匐する小さな多年生食虫植物です。
葉には気中葉と沈水葉の2種類があります。
葉は小さく気中葉はヘラ状をしており、沈水葉は線形をしています。
青紫色の花を自生地では8〜10月に咲かせますが、温室などで加温栽培すると1年中咲いています。
花の形は、短い距を下に持つ唇形で基部に萼片があります。
花後に果実(霶果)を成らせます。
花後に残った萼片が果実を包んだ姿が耳掻きの頭のようになることが命名の由来です。
一般名:ムラサキミミカキグサ(紫耳掻き草)
■関連ページ |

「比較の対象がないので大きさが分からないわね」

「うんと小さいのよ。色は青っぽい紫色」

「それで、水中に虫捕り袋があるの」

「花名は花後に残った萼片が耳掻きみたいに見えることから」
ムラサキミミカキグサ(紫耳掻き草)
夢の島熱帯植物館で、2011年1月16日