ミツバチ(蜜蜂)【かぎけんWEB】
ミツバチとはハチ目ミツバチ科ミツバチ属の昆虫です。
西洋蜜蜂のイラスト |
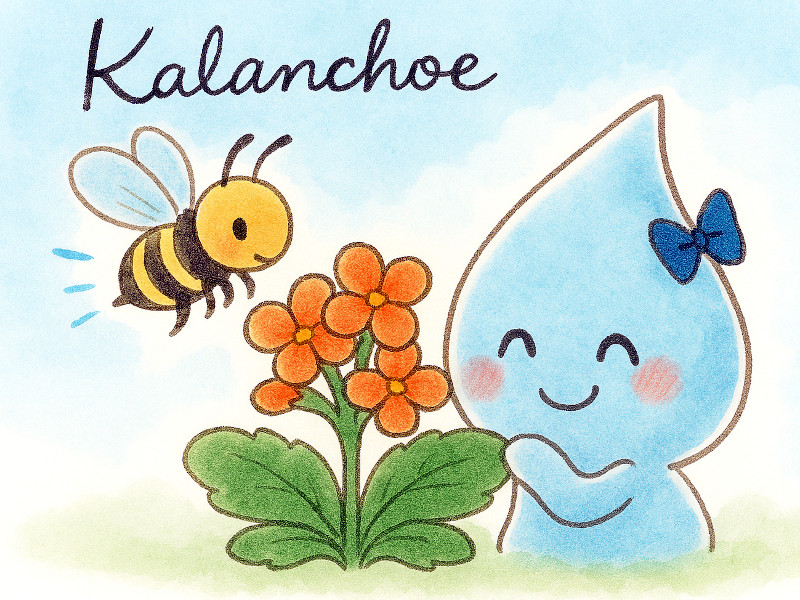
蜜蜂、カランコエ(学名:Kalanchoe)、アクアちゃん。
西洋蜜蜂の写真 |
蜜蜂とは
ミツバチ(蜜蜂、学名:Apis)とはハチ目ミツバチ科ミツバチ亜科の昆虫です。英名では、Honey beet(ハニービー)と呼ばれます。
蜂蜜をとることや作物の受粉に役立つ働き者です。
虫媒花の場合、果実が結実には蜜蜂などの仲介が必要です。 ミツバチは雌蕊に雄蕊の花粉を運び、その見返りとして花蜜を貰います。 しかし、最終的には人間に回収されてしまいますが、..。
ミツバチの世界には1匹の生育が早い大きな女王バチがいて、1匹で巣作りを始めます。 巣が出来たら、多数の小さな働きバチと雄バチを産みます。
蜜蜂の身体の大きさ
女王バチは1.3〜2cm、働きバチは1〜1.4cm、雄バチは1.2〜1.7cmです。 卵から成虫に生育する日数は、女王バチは15〜16日、働きバチは19〜21日、雄バチは21〜24日です。ミツバチの種類−二ホンミツバチとセイヨウミツバチ
日本には二ホンミツバチとセイヨウミツバチの2種がいます。二ホンミツバチ
ニホンミツバチは在来種でセイヨウミツバチより身体が少し小さく、黒っぽい。蜜の採取に関して、採取する蜜量は少なく、独自の巣作りをするので、蜜の回収が難しいです。性格は臆病で人を刺すことはめったにない。セイヨウミツバチ
明治時代に養蜂用に輸入され全国で飼育されています。身体は二ホンミツバチより一回り以上大きく、働きバチの腹部は黄色い。養蜂ではセイヨウミツバチの方が一般的で、巣箱で大量に飼育し採蜜が容易です。マルハナバチ
ミツバチの他に、花蜜を運ぶ昆虫に「マルハナバチ(丸花蜂、学名:Bombus)」がいます。マルハナバチには、/コマルハナバチや、トラマルハナバチ、オオマルハナバチ、クロマルハナバチなど、十数種がいます。
ミツバチとマルハナバチの違いどちらもハナバチの仲間 |
||
| ミツバチ(蜜蜂、学名:Apis) | マルハナバチ(丸花蜂、学名:Bombus) | |
| 体形 |

写真はセイヨウミツバチ 身体は細長くスマート。 頭は黒、ニホンミツバチはセイヨウミツバチより小さい。 ニホンミツバチは胸部は茶色、胴体は茶色の濃淡のある縞模様 セイヨウミツバチは体が黄色っぽく、胴体の縞はお尻の方が広い |

身体はミツバチより大きく、丸くてずんぐり、頭は黒。 トラマル:胸部は鮮橙色 コマル:全体黒、お尻は橙色 オオマル:全身黒、お尻は橙色、胸と腹に白帯。 クロマル:全身黒、お尻は橙色で黒帯が入る。 |
| 活動期 | 春から秋の昼間 | 一年中 |
蜜蜂の天敵
オオスズメバチ、キイロスズメバチ(黄色雀蜂、学名:Vespa simillima、ベスパ)はミツバチより身体が大きく肉食で攻撃的です。蜜蜂が大好きな花
受粉の媒体の種類
受粉の媒体として虫、鳥、風、水などがあります。虫媒花
西洋蜜蜂やマルハナバチが媒介する花や植物には被子植物の多数イチゴ、メロン、スイカ、サクランボ、ミカン、トマト、茄子、アーモンドなど地球上の植物の3分の1程があります。
虫媒花以外1−鳥媒花
ハチドリやミツスイなどによる虫媒花以外2−風媒花
風の力で空気中に散布して受粉させる。虫媒花以外3−水媒花
水の流れを利用して花粉の受粉を行う。一般名:ミツバチ(蜜蜂)、
学名:Apis、
英名:Honey beet(ハニービー)、
分類名:動物界節足動物門昆虫綱ハチ目ハチ亜目ミツバチ上科ミツバチ科ミツバチ亜科ミツバチ属、
生息分布:本州〜九州の日本、
体長:女王バチは1.3〜2cm、働きバチは1〜1.4cm、雄バチは1.2〜1.7cm、
外敵:オオスズメバチ、キイロスズメバチ(黄色雀蜂、ベスパ、学名:Vespa simillima)、
用途:ハチミツをとることや作物の受粉。
■関連ページミツバチ(蜜蜂) 帯広出張−明希(2014年8月6日〜7日) 昆虫図鑑 虫/両生類 麹町便り memo |
蜜蜂の大きな写真 |


マンゴーの花の蜜を吸うミツバチ
北海道で、2014年8月、藤田明希撮影


